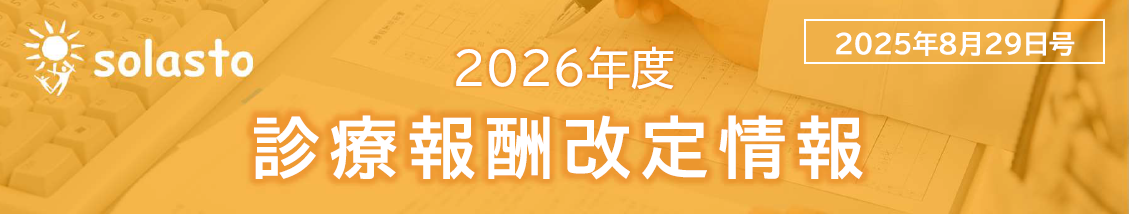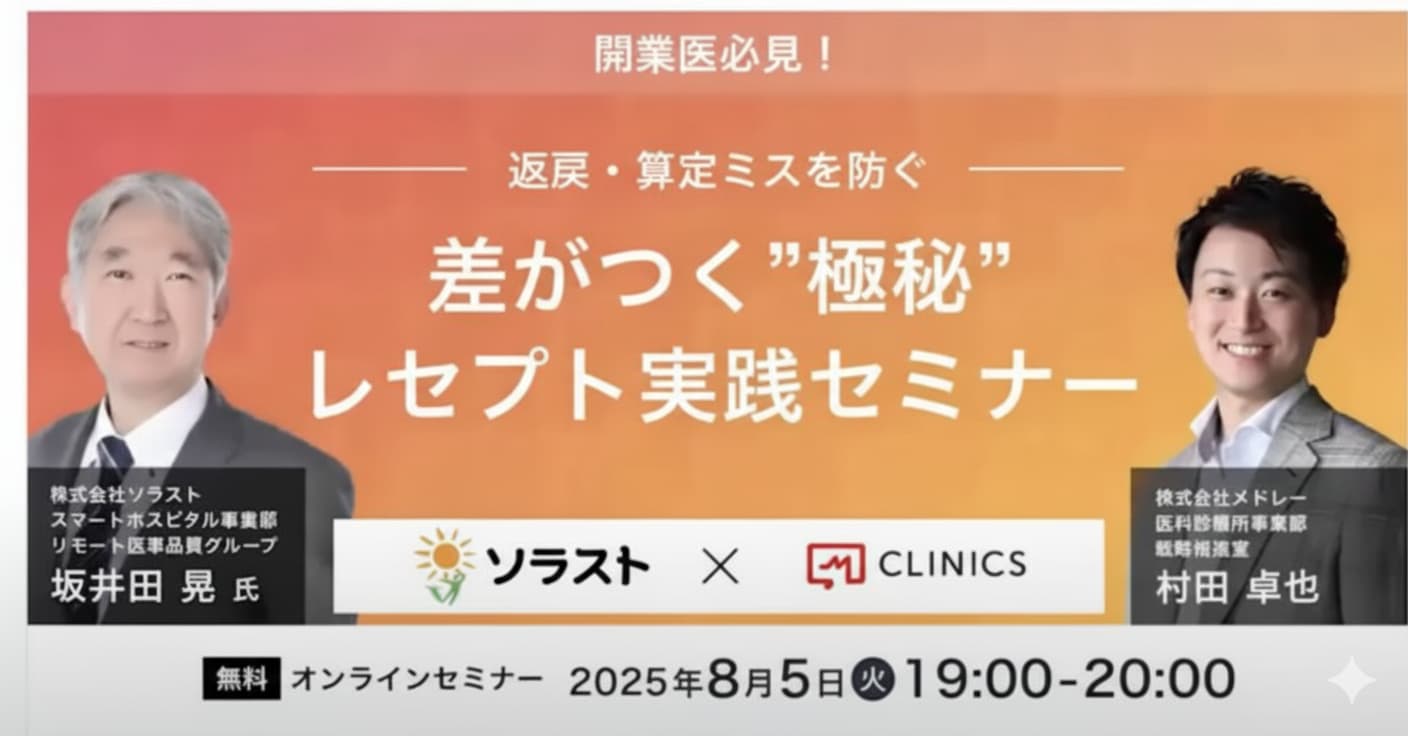病診連携とは?病病連携との違いや実施するメリット・システム課題を解説


人手不足の中、効率的かつ質の高い医療提供のために病診連携など複数の医療機関が、地域で連携していくことが必要といわれています。しかし、実際にはどのようなことを指すのかご存じでしょうか?この記事では、病診連携について病病連携などとの違いや連携のメリット、今後の課題などを解説してきます。ぜひ、ご覧ください。
病診連携とは?

病診連携とは、地域の病院と診療所がお互いに患者さんの情報を密にやり取りする体制のことです。これにより患者さんは、複数の医療機関の専門性や役割に基づいたサービスを総合的に切れ目なく受けられます。また、病院などの医療機関は地域に求められる役割を全うしやすくなるため、提供できるサービスの質の向上が図れます。
必要な人に必要な医療を提供しやすくなるため、限られた医療資源の効率的な活用へつながっていくでしょう。
参照:厚生労働省「医療施設経営安定化推進事業地域での医療に係る機能分化・連携が与える医療施設経営への影響 調査研究」
病診連携の基本的な仕組み
病診連携の基本的な仕組みは、病院と診療所が互いに患者さんを紹介しあうことです。たとえば、診療所は専門的な治療が必要な場合は、病院へ患者さんを紹介します。一方、病院では症状が安定し通院治療が可能になった患者さんを診療所へ紹介し、フォローアップを依頼します。
このように、相互の強みを活かし弱みを補完することで、地域全体の医療の質を向上が期待できるでしょう。
病病連携・地域医療連携との違い
| 種類 | 病診連携 | 病病連携 | 地域医療連携 |
|---|---|---|---|
| 定義 | 「病院」と「診療所」が患者さんの情報を共有し、適切な医療を提供するための連携体制 | 「病院」と「病院」が患者さんの情報を共有し適切な医療を提供するための連携体制 | 患者さんを中心に医療・介護・福祉などの機関が包括的に連携する体制 |
| 特徴 | ・患者さんの症状の程度に合わせて、診療所から病院へ紹介、病院から診療所へ逆紹介を行う ・地域医療連携の一部 |
・症状に応じて機能分化した病院間の連携 ・地域医療連携の一部 |
・医療以外の福祉や介護など多職種を含めたネットワーク状の連携 ・地域の医療資源を適切に分配する |
病診連携とよく似た用語に、「病病連携」や「地域医療連携」があります。病病連携は、異なる機能をもった病院同士が連携することです。これにより、患者さんの症状に合わせた治療を適切に効率よく行えます。
それに対し、地域医療連携は医療機関に限らず、介護や福祉など多職種を含めた地域全体での包括的な連携です。入院から在宅生活まで必要なサービスを効率的に提供できます。
「病診連携」と「病病連携」は、地域医療連携を果たすための連携体制の一つです。3つの連携体制は、相互に補完し合うことで地域の医療の質を向上させています。
病診連携の具体的な取り組み
病診連携の取り組みが、これから重要になるのはよくわかります。しかし、その実現のため、どのようなことを行えばよいのでしょうか。ここからは、具体的な取り組みを4つ挙げ、それぞれ解説していきます。
医療機関同士の紹介・逆紹介
医療機関同士の紹介・逆紹介は、患者さんの状態に応じて最適な医療機関へ紹介を行う取り組みです。具体的には、かかりつけ医がより高度で専門的な治療が必要と判断した場合に、病院への紹介状の作成することが挙げられます。また、病院は急性期治療後にかかりつけ医へ患者さんを紹介する、逆紹介も連携例の1つです。
このように地域の医療機関の間で、患者さんの診療情報を共有することは切れ目なく質の高い医療を効率的に提供へつながります。
開放型病床の活用
開放型病床は、診療所医師が病院で患者さんの治療を継続できる取り組みです。診療所医師は病院の登録医制度を利用し、病院の医療設備を活用しながら患者さんの治療が行えます。患者さんにとっても、入院中も主治医から継続的な診察を受けられるので安心できるでしょう。
また、病院は症状が安定した患者さんを、診療所医師に任せられます。専門的な治療を必要とする患者さんに集中できるので、業務負担の軽減が図れ、より質の高い医療の提供へつながります。
医療機器の共同利用
医療機器の共同利用は、登録している診療所医師にCTやMRIなど高額医療機器の使用を許可する取り組みです。診療所医師は医療機器を必要なときに使用できるので、検査結果をすぐ診療に活用できます。
このように、効率的に医療機器を運用することで、待ち時間の軽減や診療の効率化につながるため、地域全体の医療の質が向上するでしょう。
病診連携室による円滑な連携
病院において病診連携室は、病院と診療所の連携を円滑にするために重要な役割を担っています。具体的には、紹介状の管理や予約調整などの実務だけでなく、地域の医療機関と良好な関係構築を促す取り組みを行います。
患者さんの情報の適切な管理と共有を通じて、安全な医療連携を実現する要です。
病診連携のメリット
| 対象 | メリット |
|---|---|
| 患者さん | ・質の高い医療を安心して受けられる ・待ち時間が短くなり、早く治療を受けられる ・症状に応じて最適な医療機関で治療を受けられる |
| 診療所 | ・病院の高度医療機器を活用し専門的な検査が実施できる ・開放型病床を利用で患者さんの継続的な診療ができる ・病院との連携強化で紹介患者さん数の増加が見込める |
| 病院 | ・重症患者さんやより高度な治療が必要な患者さんに集中できる ・外来患者さん数が適正化し医療スタッフの負担が軽減する ・効率的な病床運営が可能になる |
病診連携にはさまざまなメリットがあります。ここでは、患者さん・診療所・病院の3つの視点から具体的なメリットをみていきましょう。
患者さんにとってのメリット
患者さんとっては、症状に応じて最適な医療機関で必要な治療を受けられることが大きなメリットです。自身の治療経過などの診療情報が共有されるため、検査の重複や投薬ミスが防止できます。
また、かかりつけ医も病院医師も一元化した経過をみて診療にあたれるため、より質の高い医療を受けられるでしょう。さらに、予約システムの活用により、診療までの待ち時間が短縮する点も大きなメリットといえます。
診療所にとってのメリット
診療所にとっては、必要に応じて高度な医療機器が活用し検査ができることがメリットです。また、開放型病床を活用し入院中も患者さんの継続的な診療が行えます。
さらに、病院との連携が強化でき、より紹介患者さんの数の増加が期待できるでしょう。地域の中核医療機関との信頼関係構築につながる面もメリットといえます。
病院にとってのメリット
病院にとっては、より高度な治療を必要とする患者さんに集中できることがメリットです。外来患者さん数の適正化が期待できるため、医療スタッフの負担軽減が可能です。
さらに、地域連携パスの活用で効率的な病床運営が可能でしょう。診療所との良好な関係を築くことで安定した患者さんの紹介が得られるのもメリットといえます。
病診連携における診療報酬

病診連携すると、さまざまな診療報酬が算定可能です。東京都医師会によると、以下の項目において診療報酬の算定ができると明記されています。
連携強化診療情報提供料(届出必要)
電子的診療情報評価料
がん治療連携指導料
退院時共同指導料(1)(入院医療機関では2を算定)
療養・就労両立支援指導料
引用:公益社団法人東京都医師会「新規開業医のための保険診療の要点(各論)[2-7] 連携(病診連携・医介連携・診療情報提供)」
診療報酬は、厚生労働省が診療行為に対して定めている点数から決められます。算定するための条件は人員や設備など多岐にわたり、細かく定められています。2年間隔で見直されるため、適宜医師会や厚生労働省などが発表する情報を確認することが大切です。
病診連携を推進する上での課題
病診連携は、患者さん・病院・診療所の3者にとって大きなメリットをもたらしてくれる情報共有システムです。しかし、まだ課題が残っており、これから改善・工夫をしていく必要があります。ここからは、残された4つの課題をみていきましょう。
円滑な情報共有システムの実現
病診連携には早く正確に患者さんの情報を共有できる円滑な情報共有システムが必須です。しかし、医療機関間でのシステムの統一化が十分とは言い切れません。具体的には、紙媒体の情報伝達は時間的ロスや伝達ミスが発生し、患者さんの個人情報の漏洩につながる可能性があります。
また、各々の医療機関で電子カルテシステムが異なる場合、データ連携が技術的に難しく、迅速な対応が困難です。患者さんの個人情報を保護しながら、円滑に情報共有できるシステムの確立が急務とされています。なお、標準型電子カルテの実装時期が近づいてきているため、現在よりもさらに連携が行いやすくなる予定です。
医療機関間の機能分担の明確化
医療機関ごとに機能分化が進んでいますが、その役割や機能分担が明確になっていない場合があります。同じような機能の医療機関でも提供可能な医療サービスにばらつきがあるのが課題です。
地域によっては医療機関の数や設備に格差があり、本来担うべき役割を果たせず、適切に分担することが難しい状況も見受けられています。
システム導入・運用の負担
病診連携において円滑な情報共有システムの構築が不可欠ですが、その整備にも負担がかかります。そのため、小規模な診療所では導入を諦めるケースが珍しくありません。
また、システムは導入後の運用や定期的な保守が必要です。しかし、そのための専門的な知識を持つ人材が不足しています。さらに、システムの更新や改修に伴い継続的なコストが発生するため、人的にも経営的にも負担が大きいことが課題です。
この共通したシステム導入や運用にかかるコストを軽減するサービスが、ソラストのリモート医事業務代行「iisy」です。50年以上医療事務の受託業務を行ってきたノウハウを活用できるだけでなく、システム導入の投資が少なくすみます。興味のある方はぜひ一度ご覧ください。
人材確保・育成の難しさ
病診連携に必要な知識や技術は多岐にわたり、専門的に担当できる人材の確保が困難なことも課題の1つです。そもそも医療情報システムを運用できる技術者が十分育っていないことや、連携業務に関する標準的な教育プログラムが整備されていないことが原因といわれています。
また、慢性的な人手不足も相まって、連携業務の質の維持やその向上が難しいことも課題といえるでしょう。
これからの病診連携に求められること

今後の地域医療に必要な病診連携ですが、今後どのように発展していくのでしょうか。ここでは、今後求められることについて紹介していきます。
地域医療構想との連携
地域医療構想と連携し、限られた医療資源を効率的に活用できる体制を整えることが、これからの病診連携にとって重要です。地域医療構想とは、2025年の医療需要と必要病床数を推計し、地域ごとの医療提供体制を計画的に構築する施策を指します。
そのため、医療機関だけでなく、介護や福祉など地域にある多職種と共同的に動けることが要になるでしょう。
・救急医療や小児、周産期医療など地域医療の中心になる病院の役割を明確化する
・中核医療機関以外の医療機関が担う機能を定め、役割を明確化する
・それぞれの役割を果たせるように連携体制や病床数の調整等を行う
医療DXの活用
医療DXの活用も患者さんの利便性向上と病院経営の効率化のために、今後の病診連携で必要なことです。デジタル技術を活用して患者さんの情報を円滑に共有することは医療スタッフの業務量の軽減だけでなく、待ち時間の短縮などにつながり、医療に対する患者さんの満足度を高めます。
さらに、必要な人に必要な医療資源がいきわたるため、限りある医療資源を最大活用することにつながるでしょう。
・カルテや問診表など紙業務のペーパーレス化
・診療の受付や問診表の記入のデジタル化
・ビデオ通話などを活用したオンライン診療
・各医療機関の診療情報などを共有し、病気の早期発見などにつなげるビックデータの活用
人材育成と体制づくり
医療情報システムを運用する技術者や連携業務に対応できる人材を育成し、活かす体制をつくることはこれからの病診連携にとって急務です。デジタル技術は適切に運用していくために保守・点検が必要で、それを行うために専門的な知識が欠かせません。
また、連携先は医療機関以外の介護や福祉の事業所なども想定されます。多様化する連携先に合わせた対応ができる人材は多くいたほうがよいでしょう。
・病診連携を担える人材の確保
・病診連携の業務を効率よく行える教育プログラムの作成
・医療DX運用のための設備投資
地域包括ケアシステムのような連携体制の構築
医療機関の経営状態や地域特性を考慮した連携モデルの確立が、病診連携には求められています。地域包括ケアシステムのような医療・福祉・介護をまとめた地域のネットワークがあることで、必要なときに必要なサービスへアクセスしやすくなります。
患者さんの利便性があがり、情報を共有しやすくなることで、最適な医療を低コストで提供することが可能になるでしょう。
・病院と地域の多職種が交流できる学術会などの開催
・地域住民への健康セミナーなど健康啓発への取り組み
・開放型病床など地域の診療所と連携しやすい設備を整える
病診連携はこれからの医療を支える仕組み
病診連携とは、病院と診療所が個々の強みを活かして連携することで、地域の医療資源を効率的に活用し、患者さんにとって安全で最適な医療を提供する取り組みです。この効果は患者さんのみならず、業務の効率化や医療スタッフの負担軽減・効率的な病床運営などにつながり、大幅なコストダウンが望めるため病院経営にも及びます。ただし、そのためには医療DXの活用や連携業務に精通した人材が必要不可欠です。
ソラストは50年以上の医療業務事業の経験・ノウハウで人材とDX活用の問題を解決できます。なかでも、リモート医事代行サービス「iisy」は煩雑な業務を任せられるため、教育などの時間を専門的技術の習得などに充てることが可能です。本来担うべき機能に特化するため、サービスを活用することは連携強化につながります。詳細は下記リンクよりご覧ください。