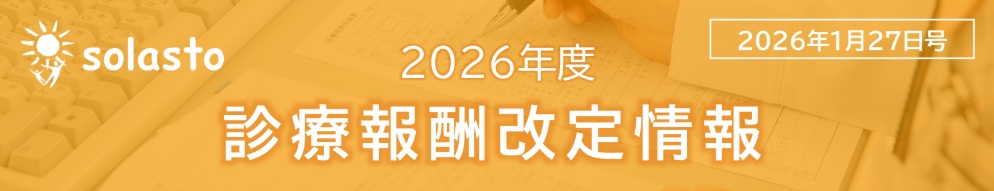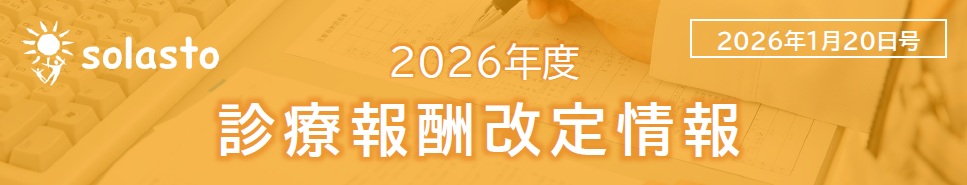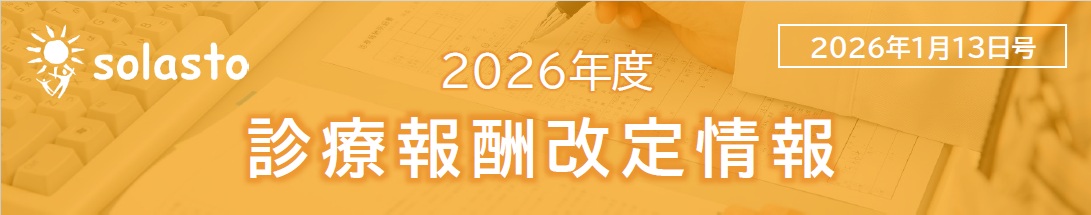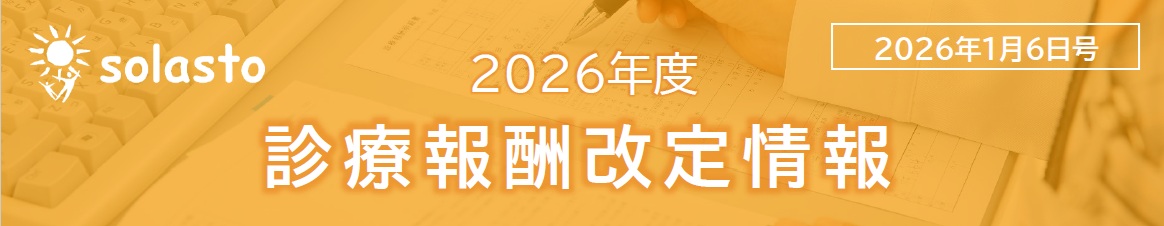タスク・シフト/シェアとは?それぞれの違いや推進する際の注意点を業務例とあわせて解説

タスク・シフト/シェアとは、医療の質向上を目指し、医師の業務の一部を他の職種に移管・共同化する取り組みを指します。医師の長時間労働の是正や医療現場の人手不足といった問題に対応し、高い医療ニーズに応えるために重要な取り組みです。今回は、タスク・シフト/シェアの概要やメリット、職種ごとの業務例や推進するうえでの注意点を詳しく解説します。
タスク・シフト/シェアとは?
| 項目 | タスクシフト | タスクシェア |
|---|---|---|
| 定義 | 医師の業務の一部を他職種に完全に移管する 「業務移管」 |
医師の業務を複数の職種で分け合う 「業務の共同化」 |
| 目的 | ・医師の業務負担軽減 ・医師の長時間労働の是正 |
・医療チーム全体での効率的な業務分担 ・協力体制の構築 |
「タスクシフト」とは、医師の業務の一部を看護師や薬剤師といった他の職種に移管して、医師の負担を軽減する取り組みです。一方「タスクシェア」とは、医師の業務を複数の他職種で分担して行う「業務の共同化」を意味し、職種を超えて協力する取り組みを指します。
タスク・シフト/シェアは、医師の長時間労働や医師数の地域偏在・従業者不足といった問題の改善を目的とした取り組みです。医療従事者の健康確保と業務負担の最適化、医療の質を向上させる施策として、位置づけられています。
なお、タスク・シフト/シェアの取り組みは、医師と看護師間に限らず、他の職種と看護師間などでも行われています。現在、約300の医療行為のタスクシフト/タスクシェアが可能と判断され、法改正も進められています。
タスク・シフト/シェアが求められる背景

医療現場においてタスクシフトやタスクシェアが求められている背景には、2018年7月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことがあります。
医師の長時間労働是正のため、2024年4月からは時間外・休日労働時間に年960時間といった上限規制が設けられました。しかし、医療の高度化や書類作成業務の増加で医師の負担は増しており、その対策が急務とされています。
従来の医師に依存した体制から多職種が連携し、効率的に医療を提供する体制構築のためにタスクシフトやタスクシェアの取り組みが進められています。
タスク・シフト/シェアのメリット
医療機関でタスクシフトやタスクシェアを進めることで、上記のようなメリットが得られます。取り組みの重要性・必要性を押さえるためにも、メリットをみていきましょう。
業務量を削減できる
タスクシフトを進めることで、医師は診断書作成や電子カルテ入力といった事務作業を医師事務作業補助者へ移管できます。事務作業に対応する時間を診療行為に充てられるようになり、より多くの患者さんを診療できるようになります。結果として医療の質の向上が期待できるでしょう。 医師の負担が軽減されることで、コア業務に充てられる時間が増えたり、業務全体の無駄削減・効率化が進んだりするメリットがあります。人材不足を解消する
現代の日本には、高齢化に伴う医療ニーズの高まりや医師の地域偏在といった課題があります。タスク・シフト/シェアによって他職種の業務範囲を拡大すれば、医師数を増やさずに医療体制を整えることが可能です。 一人の医療職に依存しない体制を構築することで、医療現場全体の人材配置を最適化できるでしょう。医療の質向上にリソースを割ける
タスクシフトやタスクシェアの取り組みによって、医師が本来行うべき専門性の高い医療行為に集中できる環境が整います。結果として、診断・治療の精度向上や患者さんと丁寧に向き合う時間が増加するなど、多くのメリットがあります。 さらに、各医療専門職が互いの知識・スキルを活かすチーム医療により、安全で質が高く効率的な医療の提供が可能となります。職種に関わりなく推進する業務例

厚生労働省は、職種に関わりなくとくに推進する業務として以下を挙げています。
② 各種書類の記載(医師が最終的に確認または署名(電子署名を含む。)することを条件に、損保会社等に提出する診断書、介護保険主治医意見書等の書類、紹介状の返書、診療報酬等の算定に係る書類等を記載する業務)
③ 医師が診察をする前に、医療機関の定めた定型の問診票等を用いて、診察する医師以外の者が患者の病歴や症状などを聴取する業務
④ 日常的に行われる検査に関する定型的な説明、同意書の受領(日常的に行われる検査について、医療機関の定めた定型的な説明を行う、又は説明の動画を閲覧してもらった上で、患者又はその家族から検査への同意書を受領)
⑤ 入院時のオリエンテーション(医師等から入院に関する医学的な説明を受けた後の患者又はその家族等に対し、療養上の規則等の入院時の案内を行い、入院誓約書等の同意書を受領)
⑥ 院内での患者移送・誘導
⑦ 症例実績や各種臨床データの整理、研究申請書の準備、カンファレンスの準備、医師の当直表の作成等の業務
引用:厚生労働省「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」
「各種書類の記載」は、医師が最終的な確認や署名を行うことを条件としています。この条件下にある場合、損保会社等へ提出する診断書や診療報酬の算定に関する書類を記載する業務などは、必ずしも医師が行う必要はなく、医師以外の職種が行うことが可能です。
ほかに、医師から入院時の医学的な説明を受けた後に行われる「入院時のオリエンテーション」なども、各職種の専門性の程度や各医療機関の体制などを踏まえて、役割分担ができます。
【職種別】タスク・シフト/シェアの業務例
では、具体的にどの職種がどのような業務をタスクシフト・タスクシェアできるのでしょうか。看護師や薬剤師などの職種別に、具体的な業務例をみていきます。
看護師
① 特定行為(38行為21区分)
② 事前に取り決めたプロトコール(※)に基づく薬剤の投与、採血・検査の実施
③ 救急外来における医師の事前の指示や事前に取り決めたプロトコールに基づく採血・検査の実施
④ 血管造影・画像下治療(IVR)の介助
⑤ 注射、採血、静脈路の確保等
⑥ カテーテルの留置、抜去等の各種処置行為
⑦ 診察前の情報収集
特定行為研修を修了した看護師は、人工呼吸管理や持続点滴中における降圧剤などの薬剤投与量の調整等、医師があらかじめ作成した手順書(プロトコール)に基づいて、特定行為を実施できます。
医師は指示出しの負担が軽減され、看護師の判断で迅速な処置を進めることが可能です。患者さんはタイムリーな医療提供というメリットを享受できます。
薬剤師
b① 周術期における薬学的管理等
② 病棟等における薬学的管理等
③ 事前に取り決めたプロトコールに沿って行う処方された薬剤の投与量の変更等
④ 薬物療法に関する説明等
⑤ 医師への処方提案等の処方支援
⑥ 糖尿病患者等における自己注射や自己血糖測定等の実技指導
プロトコールに基づいた薬剤の投与量の変更などの業務は、本来薬剤師が対応できる業務であったものの、医師が代わりに対応している現状があります。そのため、タスク・シフト/シェアの目的からすると、医師ではなく薬剤師が対応することが本来の姿といえます。
臨床検査技師
① 心臓・血管カテーテル検査、治療における直接侵襲を伴わない検査装置の操作
② 負荷心電図検査等における生体情報モニターの血圧や酸素飽和度などの確認
③ 持続陽圧呼吸療法導入の際の陽圧の適正域の測定
④ 生理学的検査を実施する際の口腔内からの喀痰等の吸引
⑤ 検査にかかる薬剤を準備して、患者に服用してもらう行為
⑥ 病棟・外来における採血業務
⑦ 血液製剤の洗浄・分割、血液細胞(幹細胞等)・胚細胞に関する操作
⑧ 輸血に関する定型的な事項や補足的な説明と同意書の受領
⑨ 救急救命処置の場における補助行為の実施
⑩ 細胞診や超音波検査等の検査所見の記載
⑪ 生検材料標本、特殊染色標本、免疫染色標本等の所見の報告書の作成
⑫ 病理診断における手術検体等の切り出し
⑬ 画像解析システムの操作等
⑭ 病理解剖
臨床検査技師は、医師からの指示を受けて、心電図や超音波などの生理機能検査、血液や尿などのさまざまな身体検査を行う職種です。
上記の業務も、本来は臨床検査技師が携われる業務であったものの、医師が担当していた現状があります。タスク・シフト/シェアの観点から、臨床検査技師はこれらの業務を医師に代わって実施するべきと考えられています。
さらに、2021年10月の法改正で業務範囲が拡大し、検査関連行為や採血業務をよりスムーズに行えるようになりました。検査説明なども含めて、医師や看護師の業務負担軽減や業務効率化の向上が見込まれています。
診療放射線技師
① 撮影部位の確認・検査オーダーの代行入力等
② 画像誘導放射線治療(IGRT)における画像の一次照合等
③ 放射線造影検査時の造影剤の投与、投与後の抜針・止血等
④ 血管造影・画像下治療(IVR)における補助行為
⑤ 病院又は診療所以外の場所での医師が診察した患者に対するエックス線の照射
⑥ 放射線検査等に関する説明、同意書の受領
⑦ 放射線管理区域内での患者誘導
⑧ 医療放射線安全管理責任者
診療放射線技師は、レントゲンやMRI、CTなどさまざまな検査を担当する職種です。
上記の業務についても、もともと診療放射線技師が対応できる内容でしたが、医師が行っている現状があります。タスク・シフト/シェアにより、これらの業務は医師ではなく診療放射線技師が実施するべき、という動きが加速しています。
臨床検査技師と同じく、診療放射線技師が行える業務の範囲も2021年10月の法改正によって、見直しが行われました。
臨床工学技士
① 心臓・血管カテーテル検査・治療時に使用する生命維持管理装置の操作
② 人工呼吸器の設定変更
③ 人工呼吸器装着中の患者に対する動脈留置カテーテルからの採血
④ 人工呼吸器装着中の患者に対する喀痰等の吸引
⑤ 人工心肺を施行中の患者の血液、補液及び薬剤の投与量の設定及び変更
⑥ 血液浄化装置を操作して行う血液、補液及び薬剤の投与量の設定及び変更
⑦ 血液浄化装置のバスキュラーアクセスへの接続を安全かつ適切に実施する上で 必要となる超音波診断装置によるバスキュラーアクセスの血管径や流量等の確認
⑧ 全身麻酔装置の操作
⑨ 麻酔中にモニターに表示されるバイタルサインの確認、麻酔記録の記入
⑩ 全身麻酔装置の使用前準備、気管挿管や術中麻酔に使用する薬剤の準備
⑪ 手術室や病棟等における医療機器の管理
⑫ 各種手術等において術者に器材や医療材料を手渡す行為
⑬ 生命維持管理装置を装着中の患者の移送
臨床工学技士は、生命維持管理装置をはじめとする医療機器の操作や管理を行うスペシャリストです。
タスクシフトの例として、手術室等での清潔野での器械出しや、医師の具体的な指示の下での全身麻酔装置や人工心肺装置の操作などが挙げられます。
臨床工学技士も、2021年10月の法改正で業務範囲が拡大され、高度化する医療における安全確保と医師の負担軽減に大きく貢献しています。
その他の職種
医師事務作業補助者は、医師の指示に基づき、診断書や診療録の代行入力、各種書類の下書き・仮作成などを行えます。医師の事務作業負担を大幅に軽減します。
また救急救命士は、法改正によって医療機関への搬送前だけでなく、救急外来での一定の救急救命処置が可能になりました。
さらに、助産師は低リスク妊婦さんの健診や分娩管理、産前産後の保健指導を担い、正常な経過の場合は医師が関わることなく対応できます。
引用:厚生労働省「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」
タスク・シフト/シェアを推進する際の注意点

タスク・シフト/シェアを推進する際は、上記のポイントに注意が必要です。
タスク・シフト/シェアへの理解を促す
タスク・シフト/シェアの目的や重要性がスタッフに十分に伝わらないと、「なぜ自分の業務が増えるのか」といった抵抗や不安が生じ、円滑な導入が妨げられる恐れがあります。重要性や緊急性の認識がないと、職種間の協力体制も構築されないでしょう。
また、誤った認識のまま業務を行うことは、医療安全上のリスクが高まりかねません。
タスク・シフト/シェアを推進するために、取り組みが進められている背景やメリット、具体的な内容について丁寧な説明と対話で職員の理解を得ることが重要です。
・全職種を対象とした説明会や研修会を定期的に開催する
・具体的な事例や成功例を共有し、メリットを可視化する
・各部署にタスク・シフト/シェア推進担当者を配置する
・質問や懸念事項に対応する相談窓口を設置する
・医療機関全体での共通認識を形成するための明確なガイドラインを作成する
移管先の業務量の負担を調整する
タスク・シフト/シェアを推進するにあたって、各職種の全体の業務量を把握し、公平な再分配や人員体制の見直しが必要です。
医師から他職種へ業務を移しても、移管先の職種もすでに人手不足で多忙な場合もあるでしょう。単純な業務移管では別の職種に業務が集中してしまい、新たな負担増大を招く恐れがあります。
特定の人に業務が集中したり、新たな役割への支援が不足したりすると、職員の疲弊やバーンアウトを招きかねません。また、負担過多によりタスク・シフト/シェアへの反発が生じる可能性も考えられます。
・事前に移管先の業務量を定量的に評価し適正な配分を計画する
・段階的な業務移管を行い、調整しながら進める
・定期的な業務量調査と必要に応じた人員配置の見直しを行う
・業務効率化ツールや支援システムの導入で全体的な負担軽減を図る
業務の理解を深める研修の時間が求められる
他職種から移管・共同化された新しい業務を安全かつ質高く行うには、専門知識や技術の習得が不可欠です。しかし、多忙な日常業務の中で研修時間を確保するのが難しいケースも多いでしょう。
研修が不十分なままでは、医療の質低下や事故のリスクを高めるだけでなく、担当する職員の不安や自信喪失につながりかねません。こうした事態を回避するには、計画的な研修の実施やマニュアルの作成・整備が効果的です。
・業務時間内に研修を組み込む制度設計を行う
・eラーニングなど時間や場所を選ばない学習環境を整備する
・実践的なシミュレーション研修で実務に即したスキルを習得させる
・メンター制度を導入し、個別指導と相談体制を確立する
・定期的な確認テストやフォローアップ研修で知識・技術の定着を図る
安全管理を徹底する
医療行為は患者さんの安全に直結するため、タスク・シフト/シェアを進めるうえで安全管理は最優先事項です。
誰がどの業務に責任を持つのか不明確だと、問題発生時に迅速・適切に対応できず、改善も困難になってしまうでしょう。
安全管理のためには、手順書の整備や職種間の密な情報共有、報告・連絡・相談の徹底が求められます。そして、万が一の際のシミュレーションなどを通じ、事故を未然に防ぐ体制強化が必要です。
・インシデント・アクシデント報告制度を強化し、事例分析と改善策を共有する
・定期的な安全管理研修と実務チェックによる質の担保を行う
・責任体制と指揮系統を明確化し、問題発生時の対応フローを整備する
タスク・シフト/シェア以外にもできる取り組みはある!
タスク・シフト/シェアだけでなく、医療機関において各職種の業務負担軽減や業務効率化を目指す方法はあります。たとえば、以下のような取り組みです。・ICTの活用・DX の推進
医療事務や医師事務作業補助者、看護補助者といったスタッフ不足で悩む場合、これらの職種の業務をアウトソーシングする方法があります。自院で直接採用活動を進める負担を軽減でき、人材不足の解消や業務の効率化につながるでしょう。
また、電子カルテやWeb問診システム、オンライン予約システムといった各種ICTツールの導入を進める方法も有効です。DXの推進により、職員が各業務に割く時間を短縮でき、負担の軽減と業務の効率化につながります。患者さんにとっても、利便性の向上や待ち時間の短縮といった面でメリットが期待できるでしょう。
医療機関経営者は、タスク・シフト/シェアに加えて、これらの取り組みを進めることが大切です。
タスク・シフト/シェアで医療の質向上を目指そう!
タスク・シフト/シェアとは、医師の業務負担軽減のため、医師が行っていた業務の一部を、看護師や薬剤師などの他の医療専門職へ移管したり、複数の職種で共同化したりする取り組みです。医師と看護師間だけでなく、看護師から看護補助者など他の職種間でも進められています。タスク・シフト/シェアを進める際は、職種ごとに移管・分担できる業務を正確に把握し、注意点を押さえたうえで慎重に進めることが大切です。
ソラストでは、医事関連受託サービスや医事関連 人材派遣・紹介サービス、医療機関経営支援サービスなど多数のサービスを展開しています。タスクシフト/タスクシェアの推進もふまえ、病院経営者さまやクリニック開業医さまの状況に合わせ、適切な支援をご提供いたします。